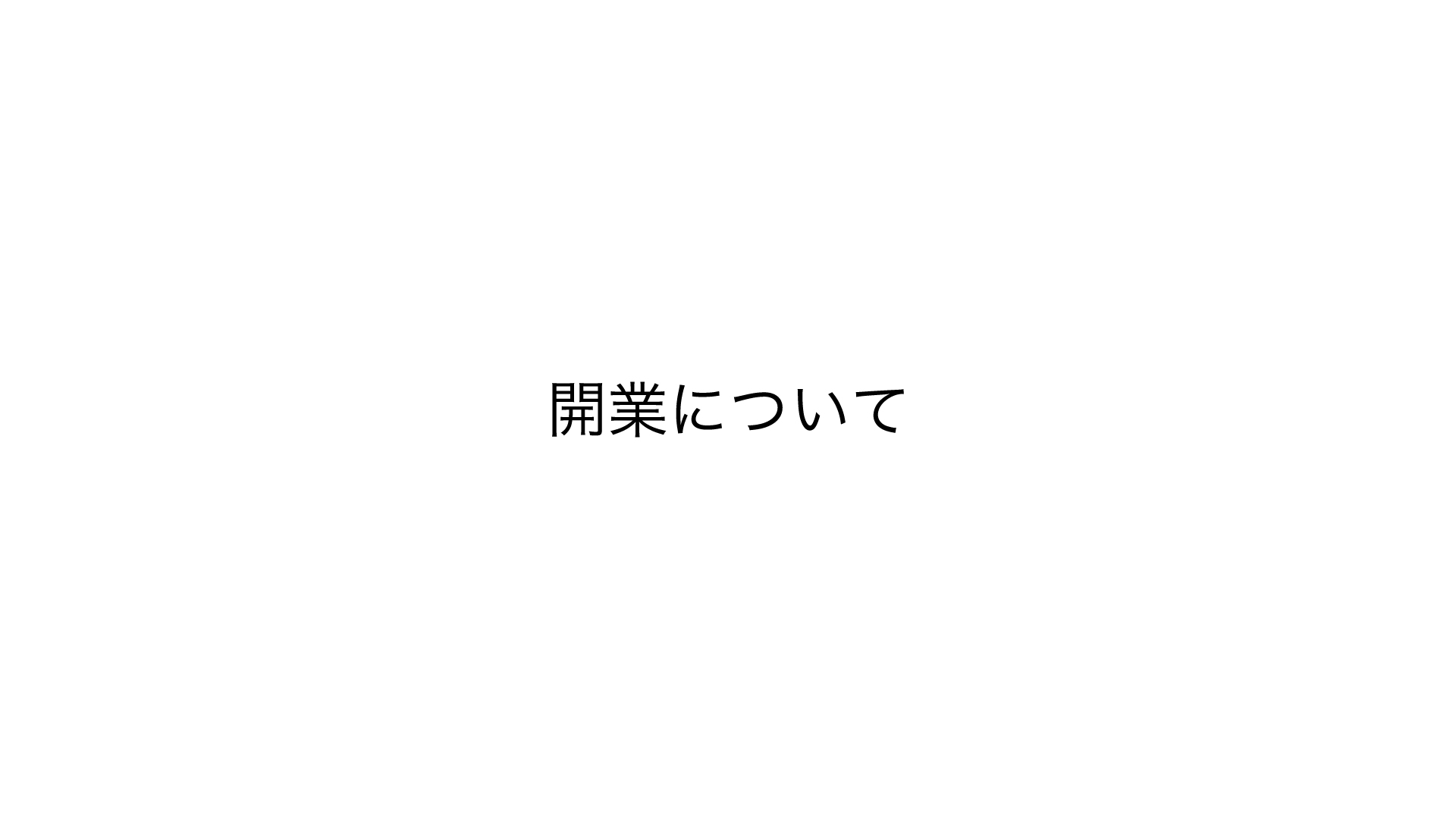京都 岡崎で個展を開く魅力とは?文化ゾーンのギャラリー周辺スポット完全ガイド
京都で個展を開催する際、会場の立地は来場者との出会いや作品の評価を大きく左右します。なかでもアートギャラリー百継がある京都・岡崎エリアは、美術館や劇場、平安神宮をはじめとする文化施設が集まる、まさに京都随一のアートゾーン。観光客や地元の人々が自然に行き交うため、個展を開くことで幅広い層に作品を届けられる絶好の環境です。この記事では、京都の岡崎エリアで個展を行う魅力とともに、周辺に点在する文化施設や観光スポットをご紹介します。
京都 岡崎で個展を開催するメリット
京都で個展を開くことは、作家にとって大きな意義を持つ経験のひとつです。なかでも岡崎は、美術館や劇場が集まる京都を代表する文化エリアとして知られ、作品を「展示するだけ」にとどまらない魅力を添えてくれる環境と言えます。作家にとっては歴史や文化に彩られた土地で自己表現できる喜びがあり、来訪者にとっても散策の途中で偶然に出会う作品が旅の思い出をより豊かにしてくれるでしょう。つまり、この地での展示は発表の場にとどまらず、作家と観客が時間と空間を共有する特別な機会を生み出します。以下では、そのメリットを五つの観点からご紹介します。
1. 来場者層と集客の期待値
岡崎エリアには美術館や劇場、動物園、平安神宮といった多様な施設が集まっており、平日には学生や研究者、休日には観光客や家族連れ、さらに国内外のアートファンまで、幅広い層が行き交います。作品展を開くことで、普段アートギャラリーに足を運ばない方々にも「ふらりと立ち寄っていただける」可能性が広がります。
2. アクセスの利便性
地下鉄東西線「東山駅」から徒歩圏内、市バスの主要停留所も点在しており、京都駅や市内各所からのアクセスは抜群です。観光動線上に位置しているため、遠方から訪れるお客様にも案内がしやすく、作家様の展示にとって集客のハードルが比較的低い環境です。
3. 周辺環境の魅力
展示の合間に立ち寄れるカフェやレストランが多く、訪れる人々にとって「作品鑑賞のあとも滞在を楽しめるエリア」です。来場者が長く滞在できる環境は、作家様にとっても作品をじっくり見ていただく機会を増やすことにつながります。
4. 文化的ブランド力
岡崎と言えば、平安神宮や岡崎公園といった京都を象徴するランドマークが集中するエリア。ここで展示を行うこと自体が、作家様の活動に「文化的ブランド力」を付与します。京都での展示歴として広くアピールできる点も大きな魅力です。
5. 展示活動の相乗効果
近隣の美術館や劇場では、国内外から注目を集める大型企画展や公演が年間を通じて開催されています。これらと同時期に展示を行えば、自然と多くの観客が流入し、より大きな注目を集めるチャンスが広がります。戦略的に展示時期を選ぶことで、作品展の影響力を高めることができるのです。
京都 岡崎の文化施設・観光スポット11選
京都の岡崎エリアは、単なる展示会場という枠を超え、作家様の活動をより豊かにし、発信力を高めてくれる舞台です。こうした文化的背景を支えるのが、ギャラリー近隣に点在する多彩な文化施設や観光スポットの存在です。この章では、岡崎地区周辺に位置している文化施設や観光スポットを具体的にご紹介します。
京都市京セラ美術館

1933年に開館した京都市美術館を前身とし、2020年に大規模リニューアルを経て「京都市京セラ美術館」として再出発しました。日本で現存する戦前建築の公立美術館としては代表的な存在と言えるこの美術館は、アールデコを思わせる端正な意匠と現代的なガラス張りの新館が調和し、訪れる人を迎えます。館内では京都画壇を中心とした日本画や現代アート、国際的な企画展など、多彩な展示が行われています。岡崎公園の緑豊かな環境と一体となり、美術鑑賞だけでなく建築散策や周辺文化施設との回遊も楽しめる、京都を代表するアートスポットです。
京都市京セラ美術館の見どころ 1.|コレクション展示「京都画壇の名作」
館の核となるのは、京都ゆかりの近代日本画コレクションです。竹内栖鳳や上村松園、橋本関雪といった巨匠たちの代表作がそろい、京都画壇の歩みを体系的に鑑賞することができます。四季折々に作品の入れ替えも行われるため、訪れるたびに新しい発見があるのも魅力。京都ならではの美術史を肌で感じられる、他では味わえない展示空間です。
京都市京セラ美術館の見どころ 2.|現代アートと国際的企画展
伝統的な日本画だけでなく、国内外のアーティストによる現代アートや国際的な企画展が積極的に開催されている点も特徴です。大型のインスタレーションや映像作品など、多様な表現が紹介され、古都・京都という文脈の中で現代美術の最前線に触れることができます。伝統と革新が同居するプログラムは、観光客だけでなくアートファンをも魅了しています。
京都市京セラ美術館の見どころ 3.|建築そのものの魅力
1933年竣工の本館は、アールデコ様式を基調とした端正な意匠が特徴で、日本の公立美術館建築として最古級に数えられます。リニューアルに際しては、建物正面に透明感あふれるガラス構造「ガラス・リボン」が新設され、歴史的建築と現代的デザインが見事に融合しました。美術品を鑑賞するだけでなく、館内外を歩きながら建築そのものを味わうことができるのも大きな楽しみです。
アートギャラリー百継から京都市京セラ美術館までの道のり(徒歩ルート)
京都国立近代美術館

岡崎公園の一角に建つ国立近代美術館は、関西で唯一の国立美術館として1963年に開館し、現在の建物は1986年に槇文彦氏の設計で竣工しました。槇文彦氏の設計によるモダンで洗練された建築は、景観に溶け込みつつも存在感を放ち、訪れる人を静かに迎えます。館内では明治以降の日本美術を中心に、絵画・彫刻・工芸・版画など幅広い分野を網羅。特に京都や関西ゆかりの作家作品が充実しており、地域文化の厚みを感じさせます。常設展示と企画展を通じて、近代から現代へとつながる美の系譜をたどれるスポットです。
京都国立近代美術館の見どころ 1.|近代日本美術の充実したコレクション
京都画壇をはじめ、関西ゆかりの作家による近代日本美術の名品が数多く収蔵されています。洋画・日本画だけでなく、工芸や版画にも力を入れており、幅広い表現をまとめて鑑賞できるのが特徴です。地域文化の土壌が育んだ多彩な作品群は、美術史を学ぶうえでも重要な位置を占めています。
京都国立近代美術館の見どころ 2.|国際的な交流と企画展
海外の美術館やアーティストと連携した企画展が数多く開催され、国内外の近代美術を横断的に体験できる点が魅力です。西洋美術との比較や、同時代における表現の広がりを実感でき、鑑賞体験に厚みを与えてくれます。日本と世界の近代美術を結ぶ架け橋としての役割を果たしています。
京都国立近代美術館の見どころ 3.|建築とロケーションの魅力
建築家・槇文彦による端正なデザインは、現代的でありながら岡崎の景観と調和し、訪れる人々に落ち着いた印象を与えます。大きな窓からは疏水や緑豊かな環境が望め、美術鑑賞とともに開放的な時間を楽しめるのも魅力のひとつ。周辺の文化施設との回遊性も高く、文化散策の起点としてふさわしい美術館です。
アートギャラリー百継から京都国立近代美術館までの道のり(徒歩ルート)
平安神宮

1895年に平安遷都1100年を記念して創建された平安神宮は、京都を代表する神社のひとつです。応天門や大極殿といった社殿は、平安京の正庁「朝堂院」を約8分の5の規模で再現したものとされ、朱塗りの柱と鮮やかな緑青の瓦が織りなす景観は壮麗そのもの。広大な境内には、四季折々の花木を楽しめる「神苑」が広がり、春の桜、初夏の花菖蒲、秋の紅葉など、季節ごとに異なる表情を見せて訪れる人を魅了します。京都岡崎の文化ゾーンを象徴するランドマークとして、国内外の観光客から長年親しまれてきました。
平安神宮の見どころ 1.|壮麗な社殿建築
平安京の朝堂院を模して造営された社殿は、左右対称に配置された伽藍と鮮やかな朱色が特徴です。大極殿をはじめ、白砂を敷き詰めた広々とした境内は、荘厳さと開放感を兼ね備えており、まるで平安時代にタイムスリップしたかのような雰囲気を味わえます。建築美と歴史的意義の両面から見応えがあります。
平安神宮の見どころ 2.|四季を彩る神苑
境内を囲む約3万平方メートルの日本庭園「神苑」は、池泉回遊式庭園として四つのエリアから成り立っています。春には紅しだれ桜が見事に咲き誇り、初夏には花菖蒲や睡蓮、秋には紅葉と、季節ごとに彩りを変える風景は圧巻です。庭園内をゆったり歩きながら、自然と伝統美が融合した景観を楽しむことができます。
平安神宮の見どころ 3.|文化行事と祭礼
1895年の創建以来続けられている「時代祭」をはじめ、平安神宮は京都の文化と歴史を今に伝える祭礼の舞台でもあります。華やかな衣装をまとった行列が都大路を練り歩く様子は、千年以上の歴史を誇る古都の文化を体感できる貴重な機会です。日常的な参拝の場であると同時に、京都の伝統行事を支える拠点でもあります。
アートギャラリー百継から平安神宮までの道のり(徒歩ルート)
京都市動物園

1903年に開園した京都市動物園は、日本で2番目に古い歴史を持つ動物園です。岡崎公園に隣接し、美術館や平安神宮など文化施設が集まる環境の中で、世代を超えて市民や観光客に親しまれてきました。2015年には全面リニューアルを終え、動物たちの自然な姿を間近で観察できる展示手法や、学びと体験を重視した施設へと進化しています。都市型動物園として規模はコンパクトながらも、工夫を凝らした展示が充実しており、大人から子どもまで楽しめる憩いの場です。
京都市動物園の見どころ 1.|動物の自然な姿を感じられる展示
新たな展示エリアでは、動物たちが生き生きと活動する姿をできるだけ自然に近い環境で観察できます。アフリカゾーンではキリンやシマウマが広々とした空間で過ごす姿を望め、ゴリラやチンパンジーの社会性を垣間見ることも可能です。来園者が「動物の生活」に寄り添える工夫が随所に施されています。
京都市動物園の見どころ 2.|教育と学びの拠点
動物を「見る」だけでなく、「学ぶ」ことにも重点が置かれています。飼育員による解説やワークショップ、子ども向けの体験プログラムなどが充実しており、環境教育の場として高い評価を得ています。命の尊さや生態系のつながりを実感できる点は、次世代を担う子どもたちにとっても大きな学びの機会となっています。
京都市動物園の見どころ 3.|憩いと交流の空間
園内は緑豊かで、芝生広場や休憩スペースも整備されており、家族や友人とゆったり過ごせる雰囲気があります。美術館や劇場を巡った後に立ち寄れる気軽さも魅力で、文化と自然の両方を楽しめるのが岡崎エリアならでは。京都市民にとっては日常的な憩いの場であり、観光客にとっては旅の合間に心を和ませてくれる存在です。
アートギャラリー百継から京都市動物園までの道のり(徒歩ルート)
琵琶湖疏水記念館

明治時代に完成した琵琶湖疏水は、京都の近代化を支えた一大事業として知られています。琵琶湖から京都市内へ水を引くことで、水運・上水道・水力発電など多方面に利用され、衰退していた京都の復興に大きな役割を果たしました。岡崎エリアを流れる疏水沿いには、四季折々の自然が彩りを添え、散策路として市民や観光客に愛されています。その歴史と役割を紹介するのが「琵琶湖疏水記念館」で、模型や映像、資料展示を通じて、京都の近代史を身近に感じられるスポットです。
琵琶湖疏水記念館の見どころ 1.|京都の近代化を支えた歴史的事業
琵琶湖疏水は1890年に完成し、当時深刻だった京都の産業衰退を救った画期的なインフラでした。舟運による物流、水力発電による電力供給、さらには日本初の営業用電車の電力供給にも活用され、京都の発展を加速させました。そのスケールと影響力は、今なお京都の近代史を象徴する存在です。
琵琶湖疏水記念館の見どころ 2.|学びを深める記念館展示
琵琶湖疏水記念館では、建設当時の資料や写真、立体模型を通じて事業の全貌をわかりやすく学べます。映像資料や体験型の展示も充実しており、技術的な挑戦や当時の人々の努力を身近に感じられるのが魅力です。観光だけでなく学習の場としても高い価値があります。
琵琶湖疏水記念館の見どころ 3.|自然と調和する疏水の景観
記念館の周辺を流れる疏水沿いは、春には桜、秋には紅葉が彩り、京都でも有数の散策スポットとなっています。水辺の景色とともに、十石舟による舟めぐりを楽しむこともでき、歴史・自然・レジャーが一体となった体験が可能です。文化施設を巡る合間に、ゆったりと自然を楽しめるのもこの地ならではの魅力です。
アートギャラリー百継から琵琶湖疏水記念館までの道のり(徒歩ルート)
南禅寺

臨済宗南禅寺派の大本山として知られる南禅寺は、1291年に亀山法皇の勅願によって創建されました。禅宗寺院の格式の中でも最高位に位置づけられ、「五山の上」に列せられる京都を代表する古刹です。広大な境内には国宝の方丈や壮大な三門などがあり、歴史と禅の精神を感じることができます。その一角にある「水路閣」は、明治時代に琵琶湖疏水を通すために建設されたレンガ造りの水道橋で、和と洋が融合した独特の景観美が多くの人を惹きつけています。
南禅寺の見どころ 1.|歴史ある禅宗の名刹
南禅寺は臨済宗の大本山として、700年以上の歴史を持つ由緒ある寺院です。境内は深い緑に包まれ、国宝や重要文化財に指定された伽藍が点在。特に三門は「絶景かな」で知られ、楼上からは京都市街を一望することができます。禅の精神と静謐な空気が漂う境内は、訪れる人に深い安らぎを与えます。
南禅寺の見どころ 2.|明治のレンガ建築「水路閣」
境内を横切るアーチ型の水路閣は、琵琶湖疏水を京都市内に引くために琵琶湖疏水の通水に合わせて明治23年(1890年)に完成しました。レンガ造りの洋風建築が古刹の境内に調和する風景は独特で、フォトスポットとしても人気です。近代土木遺産でありながら、庭園や伽藍と不思議な調和を見せる姿は、南禅寺を象徴する光景のひとつです。
南禅寺の見どころ 3.|庭園と自然美
南禅寺には小堀遠州が作庭したと伝わる枯山水庭園をはじめ、静かに水を湛える池泉庭園など、四季折々の自然と調和した庭園美があります。春の桜や秋の紅葉の名所としても名高く、訪れる時期によってさまざまな表情を楽しめます。水路閣や歴史的建築とともに、自然と調和した景観美を味わえるのが大きな魅力です。
アートギャラリー百継から南禅寺までの道のり(徒歩ルート)
永観堂

正式には「禅林寺」と称する永観堂は、平安時代の仁寿3年(853年)に空海の弟子・真紹僧都によって創建された古刹です。浄土宗の一分派である西山禅林寺派の総本山として知られ、京都でも有数の紅葉名所として多くの人々に親しまれています。本尊の「みかえり阿弥陀」は、振り返る姿の珍しい仏像として広く知られ、参拝者の心を惹きつけています。山裾に広がる境内は起伏に富み、堂宇が回廊でつながる独特の造りで、歩くごとに景色が変わる風情豊かな寺院です。
永観堂の見どころ 1.|みかえり阿弥陀像
永観堂を象徴する本尊・阿弥陀如来像は、顔を左に振り返る「みかえり」の姿で知られています。永観律師が念仏を唱えていた際、阿弥陀如来が振り返って「永観、遅し」と声をかけたという伝承に基づき、その姿が刻まれました。正面を向かない阿弥陀像は極めて珍しく、訪れる人々に深い印象を残します。
永観堂の見どころ 2.|紅葉の名所としての魅力
「もみじの永観堂」と呼ばれるほど紅葉の名所として知られ、秋には境内全体が鮮やかな朱や橙に染まります。放生池に映り込む紅葉や、堂宇と紅葉が織りなす景観は京都随一の美しさ。夜間にはライトアップも行われ、幻想的な雰囲気の中で紅葉狩りを楽しむことができます。
永観堂の見どころ 3.|起伏に富んだ境内と堂宇
山の斜面に沿って建てられた伽藍は、回廊で結ばれており、歩くごとに視界が開けたり閉じたりと変化に富んでいます。多宝塔からは京都市街を一望でき、四季折々の自然とともに風光明媚な眺めを堪能できます。境内を巡ること自体がひとつの体験となり、訪れる人を飽きさせません。
アートギャラリー百継から永観堂までの道のり(徒歩ルート)
金戒光明寺

「黒谷さん」の愛称で親しまれる金戒光明寺は、浄土宗大本山のひとつに数えられる寺院です。承安5年(1175年)、法然上人が比叡山を下りて初めて草庵を結び、念仏の教えを広めた地とされ、浄土宗の発祥の地と伝えられています。広々とした境内には三重塔や阿弥陀堂、御影堂などが点在し、落ち着いた雰囲気の中に歴史の重みを感じられます。また、幕末には会津藩の本陣が置かれたことでも知られ、京都の歴史を語る上で欠かせない存在です。
金戒光明寺の見どころ 1.|御影堂と阿弥陀堂
本堂にあたる御影堂には法然上人の木像が安置され、阿弥陀堂には本尊の阿弥陀如来坐像が祀られています。どちらも静かな環境で参拝でき、浄土宗開宗の精神を今に伝える場所です。法然の足跡を辿りながら手を合わせることで、信仰の原点に触れる体験ができるでしょう。
金戒光明寺の見どころ 2.|歴史を刻む塔頭と史跡
境内には三重塔をはじめとする塔頭寺院があり、散策するだけで多様な伽藍を目にできます。幕末には会津藩の本陣が置かれ、新選組や京都守護職と関わりのある史跡も残っています。宗教施設でありながら、近世から近代にかけての京都の舞台となった歴史を肌で感じられるのが特徴です。
金戒光明寺の見どころ 3.|四季を彩る境内景観
春の桜や秋の紅葉が境内を美しく彩り、塔や堂宇を背景とした景観は一層趣を増します。特に秋の特別公開では、多宝塔から望む洛中の景色や庭園の紅葉が多くの参拝者を魅了します。自然と建築が調和した風景は、訪れる人に穏やかな時間を与えてくれるでしょう。
アートギャラリー百継から金戒光明寺までの道のり(徒歩ルート)
哲学の道

京都・左京区の北白川から若王子神社まで約2kmにわたって続く「哲学の道」は、琵琶湖疏水の分線に沿って整備された桜並木の散策路です。春には約400本の桜が咲き誇り、運河沿いに舞い散る花びらが水面を覆う景観は京都を代表する風物詩となっています。その名は京都大学の哲学者・西田幾多郎らがこの道を思索しながら歩いたことに由来し、知の香り漂う道としても知られています。四季折々の自然とともに、文学や芸術に触れる雰囲気を味わえる人気の散策スポットです。
哲学の道の見どころ 1.|四季折々に彩られる桜並木
春の満開の桜はもちろん、初夏の新緑、秋の紅葉、冬の静けさと、季節ごとに異なる景観を楽しめるのが哲学の道の魅力です。特に桜のトンネルが作り出す光景は圧巻で、多くの観光客や写真愛好家を引き寄せます。日常の散歩道でありながら、まるで絵画のような風景に出会えるのが魅力です。
哲学の道の見どころ 2.|文化人ゆかりの道
名称の由来となった哲学者・西田幾多郎をはじめ、多くの文化人や芸術家がこの道を歩み、思索にふけったと伝えられています。道沿いには歌碑や文学碑も点在しており、単なる散策路を超えて、知的・文化的な背景を感じ取れる場でもあります。芸術に関心のある人にとって、特別な意味を持つ散策路です。
哲学の道の見どころ 3.|周辺の寺社との回遊性
道沿いには銀閣寺、法然院、永観堂など名刹が点在し、散策とあわせて寺院巡りを楽しめます。琵琶湖疏水のせせらぎを聞きながら歩けば、自然と文化が調和した京都らしい時間を満喫できます。徒歩で気軽に回遊できる点は、観光客にとっても大きな魅力となっています。
アートギャラリー百継から哲学の道までの道のり(徒歩ルート)
ロームシアター京都

岡崎公園に位置するロームシアター京都は、音楽・演劇・舞踊・映画など、多彩な舞台芸術が上演される京都を代表する文化拠点です。1960年に前川國男設計の「京都会館」として開館し、2016年のリニューアルでは香山壽夫氏の設計によって現代的な文化拠点へと生まれ変わりました。既存建物の意匠を活かしつつ現代的な機能を融合し、大ホール(メインホール)をはじめ中ホール、サウスホール、さらに自由に使えるパブリックスペースを備え、市民や観光客が芸術に触れる場として親しまれています。
ロームシアター京都の見どころ 1.|多彩な舞台芸術を楽しめるホール群
最大約2,000席を誇るメインホールをはじめ、中規模の公演に適したサウスホールや、音楽や演劇に対応できるフレキシブルなスペースが整備されています。クラシック音楽から現代演劇、舞踊や映画上映まで幅広いプログラムが展開され、国内外のアーティストによる上質な舞台芸術に触れられるのが大きな魅力です。
ロームシアター京都の見どころ 2.|建築の美と公共空間としての開放感
1960年竣工の京都会館のデザインを継承しつつ、新しい時代の文化拠点として生まれ変わった建築は、重厚なコンクリートと温かみある木質素材が調和しています。ガラス張りのロビーや広々とした中庭は、芸術に触れる場であると同時に市民が憩う公共空間として機能し、文化施設でありながら開放感にあふれています。
ロームシアター京都の見どころ 3.|蔦屋書店とスターバックスコーヒー併設の利便性
京都岡崎 蔦屋書店とスターバックスコーヒーが併設されており、公演や展示の前後に立ち寄れる憩いのスポットとなっています。芸術や建築に関する書籍が充実している蔦屋書店で知的好奇心を刺激しつつ、スターバックスで一息つけるのは、岡崎エリアでの過ごし方をより豊かにしてくれる魅力のひとつです。
アートギャラリー百継からロームシアター京都までの道のり(徒歩ルート)
京都市勧業館 みやこめっせ

岡崎公園の一角に位置する「京都市勧業館 みやこめっせ」は、京都市内有数の規模を誇る展示場として知られ、年間を通じてさまざまなイベントや展示会が開催される多目的施設です。地元の伝統工芸から現代アート、国際的な見本市や学会まで幅広く利用され、京都の産業・文化・芸術を発信する拠点となっています。館内には「京都伝統産業ミュージアム」も併設されており、京都ならではの職人技に直接触れることができます。アクセスの良さと規模の大きさを兼ね備えた文化・産業交流の舞台として、市民や観光客に広く親しまれています。
京都市勧業館 みやこめっせの見どころ 1.|多彩なイベントと展示会
「みやこめっせ」では、美術展やクラフトフェア、国際会議や産業見本市など、多岐にわたる催しが年間を通して開催されています。広大な展示ホールと機能的な会議室を備え、大規模イベントから市民向けの催しまで柔軟に対応可能。訪れる人にとって、思いがけない分野の文化や産業に出会える場所です。
京都市勧業館 みやこめっせの見どころ 2.|京都伝統産業ミュージアム
館内に併設されたミュージアムでは、西陣織、京焼・清水焼、京友禅など、京都が誇る74品目の伝統工芸品を常設展示。職人による実演やワークショップも行われ、単なる展示鑑賞にとどまらず「作り手の技と心」に触れられる貴重な体験ができます。観光客にとっては京都文化を深く理解できる学びの場でもあります。
京都市勧業館 みやこめっせの見どころ 3.|利便性と文化ゾーンとの一体感
地下鉄東西線「東山駅」から徒歩圏内というアクセスの良さに加え、平安神宮や美術館、ロームシアター京都などが隣接しており、岡崎エリア全体を回遊しながら楽しめるのが大きな魅力です。観光とビジネス、伝統と現代が交差する「みやこめっせ」は、京都の多面的な魅力を一度に体感できる施設と言えるでしょう。
アートギャラリー百継から京都市勧業館 みやこめっせまでの道のり(徒歩ルート)
まとめ ― 岡崎で個展を開くならアートギャラリー百継へ
文化施設や観光スポットが集積する京都・岡崎は、個展を開催する場として類まれな魅力を持っています。美術館や神社を巡る人々が行き交う環境は、作家にとって新たな出会いを生み、来訪者にとっても作品との偶然の出会いを楽しむ舞台となります。その中心に位置する アートギャラリー百継は、現代的な設備と落ち着いた空間を備え、作品の魅力を最大限に引き出すことができます。岡崎という文化的ブランド力を背景に、展示活動をより豊かなものにしたいと考える作家様は、ぜひ当ギャラリーでの開催をご検討ください。
参考サイト
京都市京セラ美術館
公式サイト:https://kyotocity-kyocera.museum/
Wikipedia:https://ja.wikipedia.org/wiki/京都市京セラ美術館京都国立近代美術館
公式サイト:https://www.momak.go.jp/
Wikipedia:https://ja.wikipedia.org/wiki/京都国立近代美術館平安神宮
公式サイト:https://www.heianjingu.or.jp/
Wikipedia:https://ja.wikipedia.org/wiki/平安神宮京都市動物園
公式サイト:https://zoo.city.kyoto.lg.jp/zoo/
Wikipedia:https://ja.wikipedia.org/wiki/京都市動物園琵琶湖疏水記念館
公式サイト:https://biwakososui-museum.jp/
Wikipedia:https://ja.wikipedia.org/wiki/琵琶湖疏水記念館南禅寺
南禅寺公式サイト:https://www.nanzenji.or.jp/
Wikipedia:https://ja.wikipedia.org/wiki/南禅寺永観堂
公式サイト:https://www.eikando.or.jp/
Wikipedia:https://ja.wikipedia.org/wiki/永観堂金戒光明寺
公式サイト:https://www.kurodani.jp/
Wikipedia:https://ja.wikipedia.org/wiki/金戒光明寺哲学の道
京都市観光協会:https://ja.kyoto.travel/tourism/single01.php?category_id=8&tourism_id=2684
Wikipedia:https://ja.wikipedia.org/wiki/哲学の道ロームシアター京都
公式サイト:https://rohmtheatrekyoto.jp/
Wikipedia:https://ja.wikipedia.org/wiki/ロームシアター京都京都市勧業館 みやこめっせ
公式サイト:https://www.miyakomesse.jp/
Wikipedia:https://ja.wikipedia.org/wiki/京都市勧業館アートギャラリー百継
公式サイト:https://webhyakkei.com/